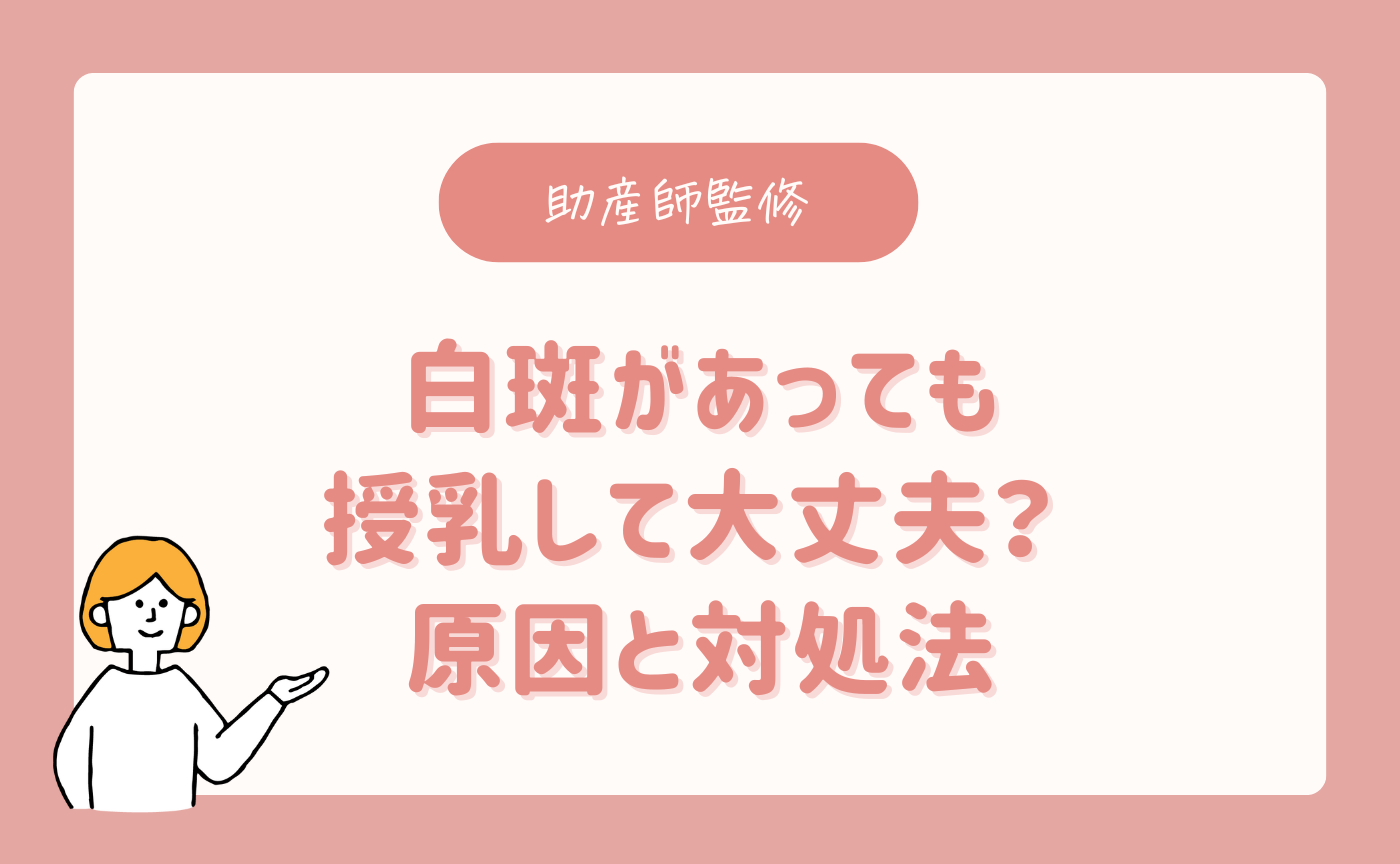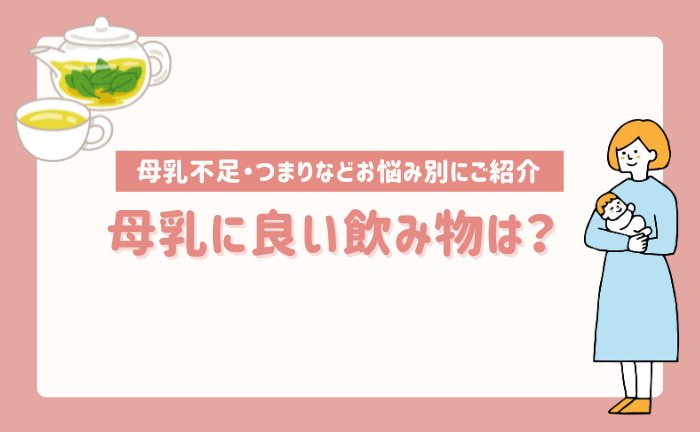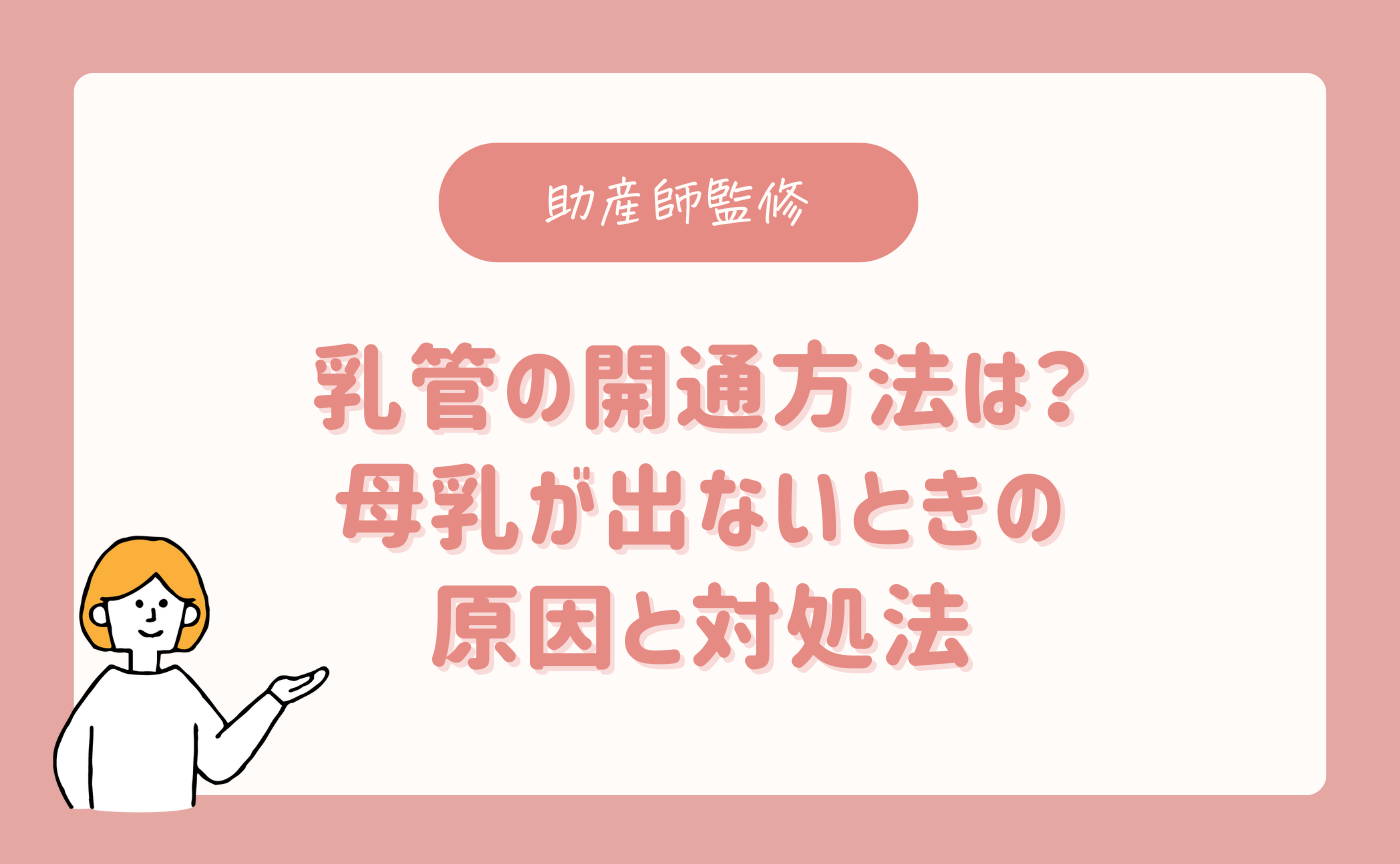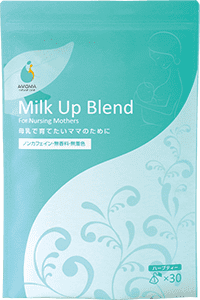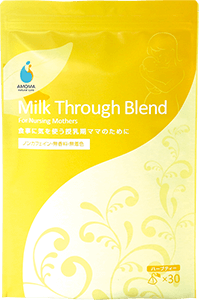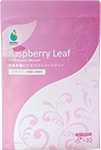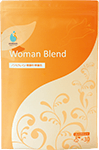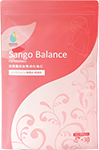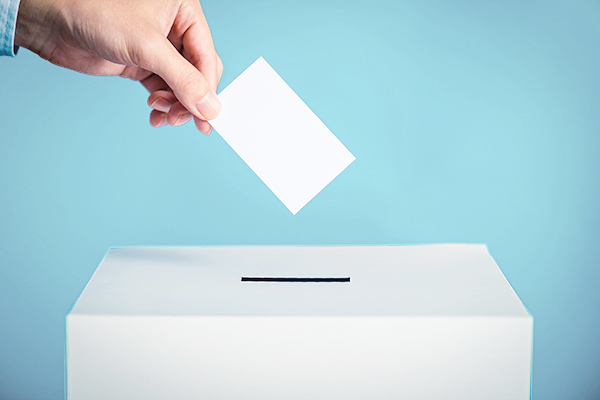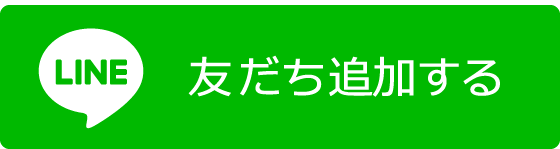【助産師監修】妊娠がわかってから出産前までにやっておくべき手続きは?
2018.12.28

ことまま
Mama writer
2017年1月生まれの女の子を育てている新米母です。夫は単身赴任なため、フルタイムで働きながら、ワンオペ育児に奮闘しています。育児疲れは仕事で癒し、仕事の疲れは娘の笑顔で癒しながら、毎日を乗り切っています。

浅井貴子
助産師
新生児訪問指導歴約20年以上キャリアを持つ助産師。毎月30件、年間400件近い新生児訪問を行い、出産直後から3歳児の育児アドバイスや母乳育児指導を実施。
タグをみる
妊娠が判明し喜びに浸るのもつかの間、実は出産までにやっておかなければならない手続きがいくつかあります。
初めてだと、何から手を付けて良いのかわからないことだらけですよね。
中には急がないものもありますが、時期が決まっているものもあります。どのようなものがあるのか早めに手続きの内容を把握し、できるものから取り掛かりましょう。
この記事では、妊娠がわかったらやるべき手続きを3つの項目でご紹介します。
その① 公的機関・医療機関での手続き

妊娠の届け出をする
妊娠がわかったら、お住まいの市区町村に届け出が必要です。
妊婦さん自身で妊娠届を記入し、提出するだけで手続きできる市区町村もありますが、医師による妊娠証明書が必要な自治体も多いようです。
検診を受けた病院で指示を受けるか、各市区町村の保健センターに確認しましょう。
届け出をすると、母子手帳を交付してもらえます。受診券や補助券がついていて今後の妊婦検診で使うことができますので、無くさないようにしましょう。
母子手帳発行の際に保健師さんが面談してくれる自治体は多いですが、届け出をした妊婦さんを保健師が家庭訪問してくれる自治体もあります。
他にも妊娠中不安なことがあれば相談ができたり、支援が必要な際の情報提供、出産後のママ・パパをしっかりサポートしてくれる自治体もあります。
分娩予約をする

妊娠が分かったら、早めに分娩する施設を決め、予約をしましょう。世間でも話題になっていますが、分娩ができる施設は減少しつつあります。
人気病院や施設の少ない地域では激戦となることもあり、出遅れてしまった場合、希望の病院がキャンセル待ちになってしまった!というケースも。
里帰り出産の方も同様に、予約が必要ですのでお忘れなく。現在のかかりつけ医にも、里帰り出産する意向を伝えておきましょう。
予約ができる期間も医療機関によりさまざまです。後期からしか受け付けていない施設もあれば、反対になるべく早めの予約をすすめられる施設もあるようです。
里帰り出産することが決まったら、まずは病院に電話して確認してみましょう。
また、妊娠◯週までに出産する病院で検診を受けること、などのルールを定めている医療機関もあります。
里帰り先が遠方で何度も検診に出向けない場合は、産休のタイミングなども確認し、早めに予定を立てておきましょう。
その② 職場での手続き

働いている人は、勤め先への妊娠報告が必要な場合がほとんどです。報告する時期について正解はありませんが、体調が悪いのを隠して勤務することで赤ちゃんに負担がかかってしまうリスクもあります。
また、会社としては仕事を引き継ぐ後任の手配も必要であり、早めに報告してくれた方がありがたい、というのが上司の本音かもしれません。
筆者の場合は、夜勤や遠方への出張業務に配慮してもらう必要もあったため、直属の上司と同僚には妊娠判明時点で知らせ、それ以外の人には安定期に入ってから伝えました。
職場の慣例も参考にしつつ、自分の体調も大切にできる時期に報告できるといいですね。退職する場合も、産休・育休を取る場合も手続きが必要ですので、ギリギリにはならないようにしましょう。
会社に産休・育休の相談

出産後も継続して働くのか、働く場合は出産予定日を伝えたうえで、産休の時期・育休の期間などを相談します。
産休や育休については、法律で定められた期間と別に、会社ごとでのルールや決まりが設けられている場合もあります。
「出産手当金」「育児休業給付金」の手続き

産休・育休中は「出産手当金」「育児休業給付金」を受け取ることができますので、勤務先の担当部署に必要書類などを問い合わせてみましょう。
なお、出産手当金や育児休業給付金を受け取るには、労働条件などで一定の基準を満たしていることが必要ですので、自分が該当しているかも調べておく必要があります。
条件を満たしていれば、正社員だけでなくアルバイトやパート、契約社員にも支給されますので、働いている方は必ず確認しましょう。
夫の手続き

夫も会社へ妻の妊娠の報告をしましょう。
夫は会社ではこれまで通り働くのだから、出産後でもいいのでは?という考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、妊娠中は思わぬトラブルで夫の助けが必要になることがよくあります。
妊娠初期は切迫流産やひどいつわり、中期以降は切迫早産などで入院となるケースもありますし、入院まではしなくても自宅安静と診断されると、夫に家事・他の兄弟児のお世話を頼むことになるでしょう。
また、出産も予定日通りとは限りませんので、立ち会い出産を予定している場合は仕事中に突然呼び出されることも考えられます。
急な休みをとることもあるかもしれませんので、そのようなケースに備え早めに会社に報告し周囲の理解を得ておきましょう。
報告する時期は決まっていませんが、妊娠が判明したばかりの初期は妊娠の継続が難しいことも珍しくありません。
万が一のことも考え、特に流産の確率が高い妊娠12週までは報告を避け、夫婦でよく相談してから会社への報告の時期を決めましょう。
育休をとる夫も年々増えているようです。育休を検討している方は早めに会社に相談しましょう。
その③ 出産に関わるお金の手続き

「出産育児一時金」の手続き
出産にいくら費用がかかるのか心配になりますよね。
健康保険に加入している妊婦さんなら全員が受け取ることのできるお金、「出産育児一時金」というものがあります。赤ちゃんひとりにつき、入院・分娩費として42万円が支給されます。
会社勤めの方は、勤務先の担当部署に必要書類などを確認しましょう。(家族の扶養に入っている場合は、扶養主の勤め先に確認してください)
自営業などで国民健康保険に入っている方は、自身で問い合わせする必要がありますのでご注意を。
「直接支払制度」を利用すれば、出産時、産院へ直接お金が支払われるので、退院時のお会計では42万円を超えた差額のみを支払うだけで済み、大金を持ち歩かなくても良いというメリットがあります。
出産予定の産院で直接支払制度の利用が可能かどうか、確認しましょう。
そのほか出産に関わるお金の手続き

この記事では詳しくは省略しますが、この他にも「出産でもらえるお金」はいろいろあります。でも、「赤ちゃんが産まれた直後」から手続きできるものがほとんどです。
妊婦のうちにできる手続きはないかもしれませんが、まずは自分がどんなお金をもらえるのか今のうちに把握し、出産後にスムーズに手続きできるようにしておきましょう。
新生児を抱えて手続きに回るのは大変です。早めに必要な書類を用意し、パートナーとも情報共有できればベター。産後は身動きが取りづらいのでパートナーに動いてもらうよう頼んでおきましょう。
また、ほとんどのお金が「自分で申請しなければ1円ももらえない」ものとなります。受け取り忘れのないよう注意してくださいね。
できるものから手続きしよう
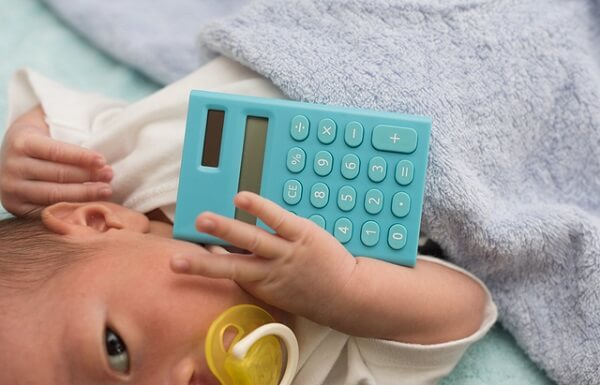
出産前にやっておくべき手続きについて、簡単にまとめました。いかがだったでしょうか?
ただでさえ大変なのに、こんなに色々な手続きまでしないといけないなんて・・・と負担に感じてしまう妊婦さんも多いかもしれませんね。
体調に配慮しながら、可能なものから手を付けていきましょう。たくさんあるときはリストを作り確認しながら進めていくと漏れがなく、家族に頼む際もわかりやすいので安心です。
ひとりで抱え込まないで、パートナーや家族にも手伝ってもらえるといいですね。
関連する記事
【助産師監修】産休・育休中にお給料はもらえる?いくらもらえるの?
【助産師監修】産後にしなければいけない手続きについて
関連記事
■体の悩み
-
 【医師監修】乳腺炎で発熱!病院に行くべき?症状・原因・対処法も詳しく解説2024.10.08
【医師監修】乳腺炎で発熱!病院に行くべき?症状・原因・対処法も詳しく解説2024.10.08 -
 【助産師監修】白斑があっても、授乳して大丈夫? 取り方などを紹介2024.10.08
【助産師監修】白斑があっても、授乳して大丈夫? 取り方などを紹介2024.10.08 -
 【助産師監修】生後1・2・3ヶ月ごとの授乳間隔・授乳回数の目安は?2024.09.17
【助産師監修】生後1・2・3ヶ月ごとの授乳間隔・授乳回数の目安は?2024.09.17
カテゴリーランキング
AMOMAコラムについて
妊娠、出産前後はママにとっては初めてのことばかり。「これってあってるのかな?」 「大丈夫かな?」と不安や疑問に思った時につい手に取りたくなるような情報をお届けしたいと考えています。そのため多くの情報は助産師をはじめ専門家の方々に監修。テーマから読めるようになっていますので、ぜひ気になるものから読んでみてください。あなたの不安や疑問が解決できるお手伝いになれば嬉しいです。
AMOMAのパートナー

看護師、助産師、IFAアロマセラピスト、JMHAメディカルハーバリスト、NCA日本コンディショニング協会認定トレーナー
母乳育児、新生児~幼児にかけての育児相談全般、アロマやハーブを使用した産前、産後ケア 代替療法全般

管理栄養士・幼児食アドバイザー
メンタルヘルス食カウンセリング、子供の心を育てる食育講座、企業向け健康経営セミナーなど

日本神経言語心理家族療法協会公認家族心理カウンセラー、NLPファミリーセラピー・マスタープラクティショナー、子どものこころのコーチング協会インストラクタ
心理カウンセラー

日本産婦人科学会会員その認定医、産婦人科専門医、日本ソフフロロジ学会会員、東京オペグループ会員、日本アロマテラピー学会会員
産婦人科医
その他のお問い合わせはこちらから
 メールで問い合わせ
メールで問い合わせ





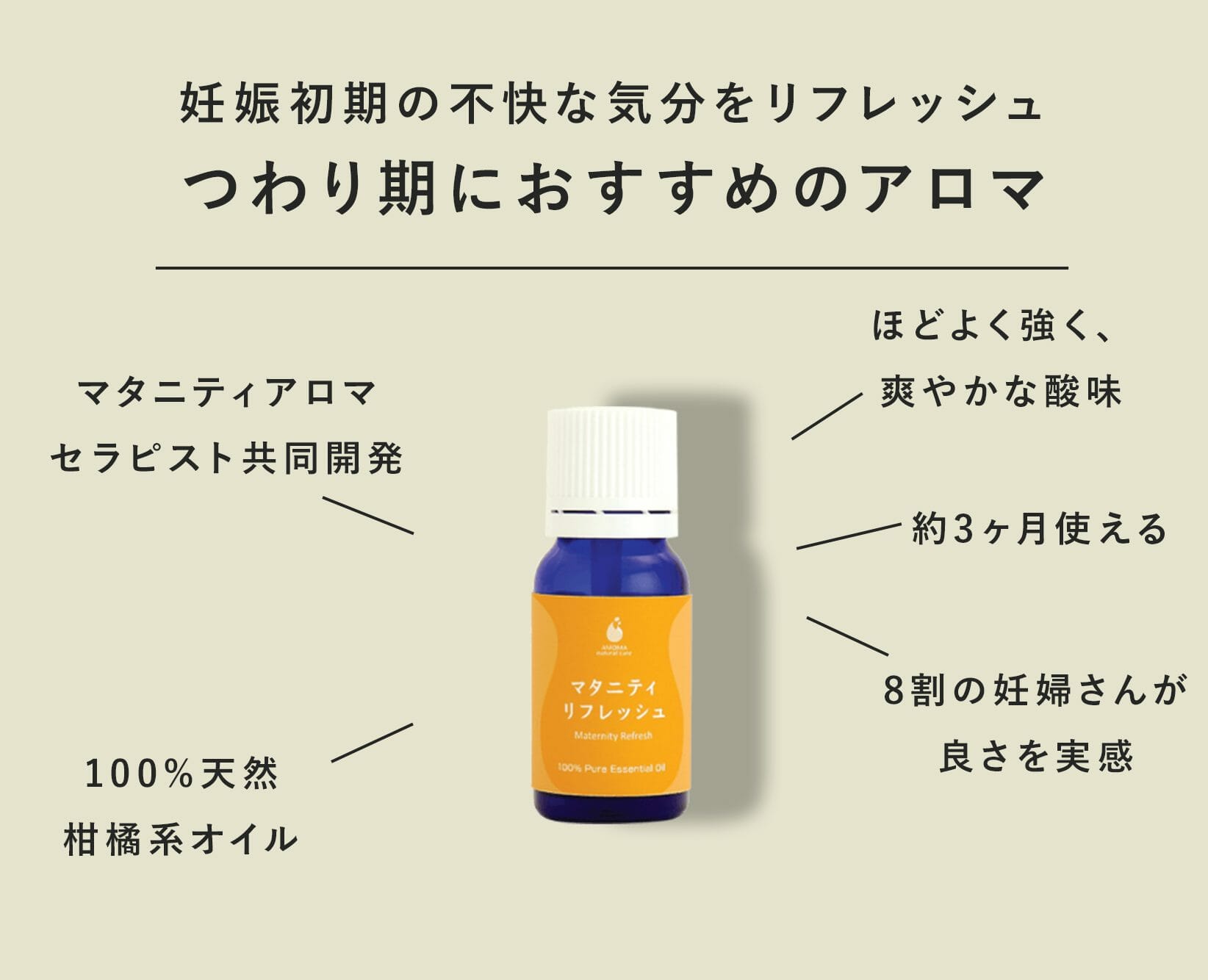

 amoma_naturalcare
amoma_naturalcare